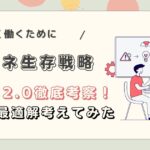ケアマネさんの時短術!
ケアプランってどうやって書くの?
文章にして表現するのが苦手だ…
ゼロから考える時間がもったいない!
といったケアマネージャーの皆様の一助になれればと思い記事を作成しました。
一つ一つの文例を検索する時間が勿体無い方は必見です!
当記事では仮の利用者を立ててケアプラン第1表〜第2表の文例を紹介しています。
似ている利用者様がいらっしゃいましたら是非文例をご活用ください!
随時更新していきます!!
認知症のケース編
87歳・認知症・下肢筋力低下・独居
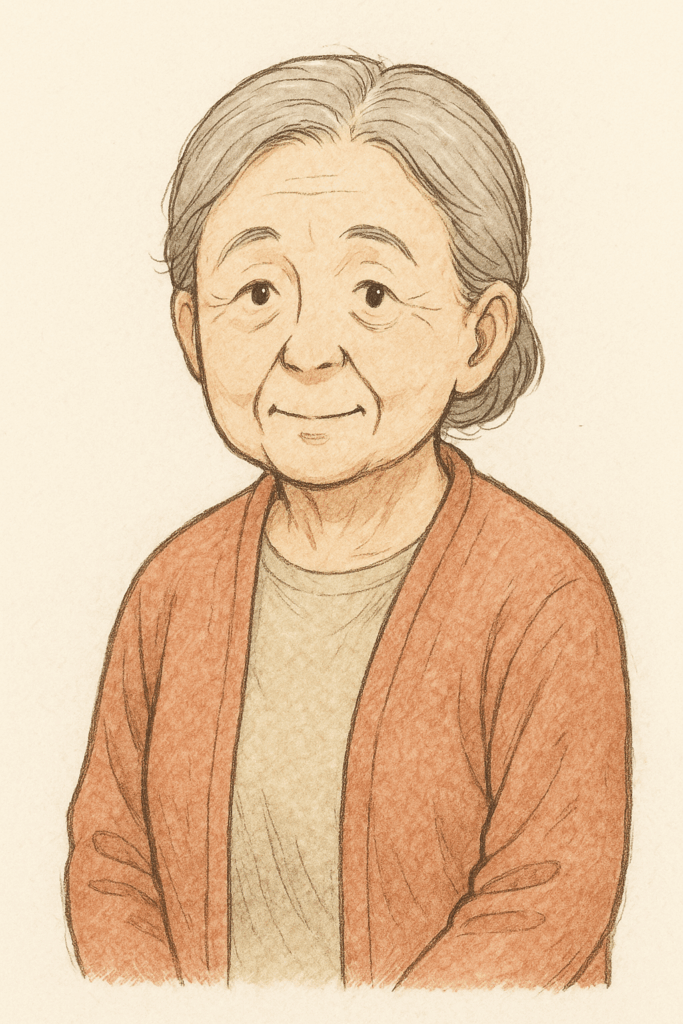
| 氏名 | Aさん |
| 年齢 | 1936年4月15日 |
| 病歴 | 高血圧、甲状腺機能低下症、認知症、心性による下肢の浮腫 |
| 状況 | 軽度認知症で独居。身の回りのことは一部可能だが、入浴・移動・服薬管理に不安あり。閉じこもり傾向も。 |
| 本人の意向 | この家で住みながら芸術活動を続けたいけど、疲れることも増えていって不安なことが増えてきた。 |
| 家族の意向 | 仕事があり遠くに住んでいる。支援するのは難しいけど家で気ままに過ごしてほしい |
| 課題分析の結果 | 利用者及び家族の意向から、自宅での生活が不安なく行えるようにし、介護サービスを利用しながら外出の機会を確保し、本人の身体機能の低下と介護者の負担を軽減していく必要がある。 |
| 総合的な援助の方針 | 定期的な受診を行いながら、病状が安定しご自身で健康管理ができるように支援します。 家の中では介護サービスを利用しながら疲れない過ぎないようにしていきましょう。 これからもA子様が生き甲斐とされている芸術活動が続けられるよう支援しハリのある暮らしを送りましょう。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
|---|---|---|---|---|
| 健康管理や服薬確認が独居では難しい。健康に気を遣いながら安心して暮らしたい。 | 定期的な健康管理で体調を安定できる。 | 適切な診察を受けて、病状が維持できる。 | ・病院内付き添い ・状態の変化を医師へ情報伝達 ・療養上の指示の確認 | 本人・家族・病院 |
| 服薬管理、確認が行える。 | ・日常的な体調管理 ・定期的な服薬状況の確認 ・病院との連携 ・24時間の緊急対応 | 訪問看護 | ||
| 屋内外の移動に不安があり、転倒してしまわないか怖い。 | 安全な住環境で安心した生活を継続できる。 | 屋内を転倒することなく移動できる。 | ・手すりの設置貸与 (安全な廊下の移動に必要) | 本人・福祉用具会社 |
| 地域での自身の役割を通し、日々に生きがいを取り戻しハリのある暮らしを送ることができる | 体調を考慮しながら、地域の活動に参加できる | ・絵画の指導、制作 ・自分の作品を展示会に出品する | 本人・友人 | |
| 友人たちと定期的に集まり趣味を楽しむ | ・カレンダーで予定を管理する ・友人が集まれるように部屋の掃除が行き届く | ・予定の管理を一緒に行う ・共同作業による家の中の掃除 | 本人・訪問介護 | |
| 物忘れがあっても、考えすぎず穏やかな心で暮らすことができる | ・毎日日記をつけて、頭を使う機会を持つ ・孫との電話で本の音読を聞きながらコミュニケーションを取ることができる | ・毎晩日記をつける ・定期的に孫と電話する | 本人・家族 |
87歳・認知症・高血圧・甲状腺低下症(訪問介護・福祉用具)

| 氏名 | A子さん |
| 年齢 | 1936年4月15日 |
| 病歴 | 高血圧、甲状腺機能低下症、認知症、心性による下肢の浮腫 |
| 生活歴 | A市生まれ。若い頃から芸術に興味を持ち、美術学校で絵画を学ぶ。美術家として認められ、展覧会での作品展示や個展が成功を収める。 美術の道に進んで、教育分野でも活躍し、美術の教師として定年まで働く。20歳で結婚し2人の息子にも恵まれ、家族とともに美術作品も制作している。 A子さんは若い世代にアートを教えることを生き甲斐にしていた。60歳のときに夫を亡くしてからは一人暮らし。地域の高齢者センターでアートイベントも主催していたが、最近、高血圧や甲状腺機能低下症の診断を受け疲れやすくなり、認知症の初期症状も見られるようになったことから地域の活動は他の人に譲るようになっている。活動と生活に支障が出てきて現在に至る。 |
| 本人の意向 | この家で住みながら芸術活動を続けたいけど、疲れることも増えていって不安なことが増えてきた。 |
| 家族の意向 | 仕事があり遠くに住んでいる。支援するのは難しいけど家で気ままに過ごしてほしい |
| 課題分析の結果 | 利用者及び家族の意向から、自宅での生活が不安なく行えるようにし、介護サービスを利用しながら外出の機会を確保し、本人の身体機能の低下と介護者の負担を軽減していく必要がある。 |
| 総合的な援助の方針 | 定期的な受診を行いながら、病状が安定しご自身で健康管理ができるように支援します。 家の中では介護サービスを利用しながら疲れない過ぎないようにしていきましょう。 これからもA子様が生き甲斐とされている芸術活動が続けられるよう支援しハリのある暮らしを送りましょう。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
|---|---|---|---|---|
| 一人暮らしで物忘れも出てきた。持病が悪化しないように正しく健康管理を行いたい | 病状が安定し、今の健康状態が維持できる | 高血圧と甲状腺機能低下症の件に関して、A病院へ定期的に受診できる(月1回) | ・車での送迎 ・病院内付き添い ・状態の変化を医師へ情報伝達 ・療養上の指示の確認 | 本人・家族・訪問介護・病院 |
| 服薬管理、血圧の確認が自分で行える | ・服薬カレンダーの使用 ・定期的な服薬状況の確認 ・血圧の測定 | 本人・家族・CM | ||
| 甲状腺機能低下症で疲れやすくなっている。ふらつくことも多くなってきたが、いつまでも自分の足で歩きたい | 家の中を1人で安全に歩くことができる | 頻繁に使うトイレや風呂、ベランダへの出入りが安全に行える。 | ・廊下、トイレ、風呂、ベランダに手すりの設置 ・シャワーチェアの使用 | 本人・福祉用具 |
| 物忘れが出てからは、地域の活動を休んでいたが、以前のように友人たちと仲良く絵を描きたい | 地域での自身の役割を通し、日々に生きがいを取り戻しハリのある暮らしを送ることができる | 体調を考慮しながら、地域の活動に参加できる | ・絵画の指導、制作 ・自分の作品を展示会に出品する | 本人・友人 |
| 友人たちと定期的に集まり趣味を楽しむ | ・カレンダーで予定を管理する ・友人が集まれるように部屋の掃除が行き届く | ・予定の管理を一緒に行う ・共同作業による家の中の掃除 | 本人・訪問介護 | |
| 物忘れがあっても、考えすぎず穏やかな心で暮らすことができる | ・毎日日記をつけて、頭を使う機会を持つ ・孫との電話で本の音読を聞きながらコミュニケーションを取ることができる | ・毎晩日記をつける ・定期的に孫と電話する | 本人・家族 |
78歳・認知症・アルコール依存症・高血圧(訪問看護・訪問介護)

| 氏名 | B太さん |
| 年齢 | 1945年11月6日 |
| 病歴 | 認知症 アルコール中毒 高血圧 |
| 生活歴 | B太さんはもともと活発で社交的な性格。地元では多くの友人を持っている。妻と息子は50歳の頃に事故で他界している。定年退職後、毎日の散歩を日課としていた。70歳の頃に物忘れが増え、散歩中に自宅の場所を忘れることが現れ警察に保護されることもあった。この認知症の症状に加えて、50歳の頃にアルコール依存症から断酒をしていたが、最近、夜中に起きてコンビニでお酒を買い際限なく飲んでしまった。地域の人が役所に相談し支援に至る。本人はできるだけ自宅で過ごしたいと考えている。地域の人もB太さんの支援に協力的。緊急連絡先は甥。 |
| 本人の意向 | これからも友人とこの町で過ごしたいと思っている。お酒は辞めたい。頼ってしまうのが恐い。家に閉じこもるのは嫌だ。 |
| 家族の意向 | 甥:本人が安全に過ごしてもらえるならそれでいいです。人との繋がりを大切にしているおじさんのままでいてほしい。 |
| 課題分析の結果 | 認知症の状況とアルコール依存症の関係を把握していくとともに、精神面でも支援が必要と考えられる。 |
| 総合的な援助の方針 | 日常生活でアルコールに頼らないよう、不安なことも知るために介護サービスを利用していきましょう。定期的な受診と薬の服用とともに、B太様の大切にしているご友人との関係も継続できるよう支援します。日課の散歩も安全に外出できるようにサポートします。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
|---|---|---|---|---|
| 今は飲んでいないが、いつか飲みにいってしまわないか不安。お酒に頼らない生活を送りたい。 | 断酒を続けられる | 定期的にアルコール依存症の自助グループ参加できる | ・例会、ミーティングに参加 ・断酒仲間との交流 | 本人、自助グループ |
| 定期受診と薬の服用が適切に行える | ・診察、投薬 | 医師、薬剤師 | ||
| 物忘れが恐いが、これからも地域の皆とこの町で過ごしたい。日課の散歩も楽しみたい。 | 心身の健康を維持し、認知症の進行を遅らせる | ・受診 ・服薬カレンダーによる服薬管理 ・健康相談、助言 | 本人、訪問看護 | |
| 不安を取り除き混乱することが少なくなる | 混乱した時に、安心できる言葉をかけてもらえたり落ち着かせてもらえる | ・共同実践による生活援助でどの場面で混乱するかを把握し対策を考える ・日常生活の相談相手になる | 本人、訪問介護、ケアマネージャー | |
| 定期的に地元のコミュニティに参加し、仲間と交流ができる | 地元で役割を持ち、充実感が味わえる | ・カレンダーでの予定の管理 ・友人と電話し、慣れない場所には複数人で行く | 本人、甥、友人 | |
| 安心して散歩ができるようになる | ・GPS端末にて場所の把握 ・散歩ルートの把握 | 本人、友人、保険外サービス |
90歳・認知症・骨粗鬆症・下肢筋力低下(訪問介護・通所リハ・福祉用具)

| 氏名 | C子さん |
| 年齢 | 90歳 |
| 病歴 | 認知症、骨粗鬆症、腰椎圧迫骨折 |
| 生活歴 | C子さんは20歳で結婚してから専業主婦として今住んでいる家を支えてきた。60歳の頃に家は全面リフォームしている。夫は85歳の頃に他界しており、2人の娘がそれぞれ月1回ずつ様子を確認しに家に来ている。認知症と骨粗鬆症の診断を受けており、88歳の頃から閉じこもりがちになり、著しい下肢筋力の低下により転倒を経験。2回の腰椎圧迫骨折もしている。現在、独歩での歩行が困難になっている。 |
| 本人の意向 | 長年住み慣れた家で、家族や友人と過ごしたい。今ある生活を大切にしたい。 |
| 家族の意向 | 遠くに住んでるが、自宅で安心して暮らせる環境を整えてあげたい。認知症の進行で他人に迷惑をかけないか心配。 |
| 課題分析の結果 | 認知症の進行、下肢筋力の低下により家事もできなくなってきている。記憶力や判断力の低下により、事故のリスクもある。 骨粗鬆症と腰椎圧迫骨折の既往歴から、転倒からの寝たきりリスクもあり安全に移動ができる支援が必要。 |
| 総合的な援助の方針 | C子さんの意思を尊重し、できる限り自宅での生活を続けるための環境整備を行います。 介護サービスを利用しながら今できることを維持していき家の中にいるだけでなく、定期的な外出や買い物等で生活にメリハリを持って過ごせるようにしましょう。 福祉用具を利用し家の中では安全に過ごせるようにし、これ以上のケガ予防に努めていきましょう。 家族以外にも、顔見知りの関係が作れるように支援します。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
| 物忘れが始まり家事をやらなくなったが、できる範囲で働きたい | できることを維持し、心身の健康を保つ | 今の身体能力でできる家事を行いやすいよう工夫できる | ・どこに何がしまってあるかわかるようにメモする ・得意料理のレシピを本人と一緒に書き出しレシピ帳を作る ・調理時、疲れた時に座れる環境を整える ・できることを増やしながら一緒に行う | 本人・家族・訪問介護 |
| 下肢の筋力低下でふらつきが多くなってきた。自分の足で歩いて暮らし続けたい。 | 現在の歩行能力や日常生活上の行為を維持することができる | 歩行支援プランを作成し、定期的に運動、リハビリが行えている | ・マッサージ、ストレッチ、筋力トレーニング ・歩行器の使用方法の助言 | 通所リハ |
| 家の中を1人で安全に歩くことができる | トイレや風呂を1人で安全に利用することができる | ・廊下、脱衣室、トイレに置き型手すりの設置 | 福祉用具貸与 | |
| 閉じこもりにならず、楽しく外出ができるようになりたい | 顔馴染みの関係が作れるようになる | 定期的に外出ができるようになる | ・行きつけの美容院に一緒に行く ・美容院でおしゃべりする | 本人・家族 |
| ・認知症カフェに参加する ・悩みや思いを話し合う | 本人・家族 |
認知症・独居(特殊寝台+手すり+歩行器・デイサービス・訪問看護・家族支援)

| 年齢 | 85歳 |
| 性別 | 男性 |
| 要介護度 | 要介護2 |
| 介護者 | 一人暮らし(娘は別居、月1回の通院送迎) |
| 既往歴 | アルツハイマー型認知症、高血圧、骨粗しょう症 |
| 状況 | 軽度認知症で独居。身の回りのことは一部可能だが、入浴・移動・服薬管理に不安あり。閉じこもり傾向も。 |
| 本人の意向 | 自分のことはできる限り自分でやりたい。お風呂には入りたいし、人と話すのも嫌いじゃない。入院せずに家で暮らしたい。 |
| 家族の意向 | できる限り今の生活を続けさせてあげたい。心配なので定期的に訪問してもらえると安心。受診の送迎などできる範囲で協力したい。 |
| 課題分析の結果 | ・認知症の進行により曜日や時間の認識に混乱があり、独居生活に不安がある。 ・屋外歩行にふらつきが見られ、転倒リスクが高い。 ・入浴や服薬など日常生活に支援が必要。 ・社会的交流が少なく孤立の傾向がある。 |
| 総合的な援助の方針 | 在宅生活の継続を支援するため、福祉用具の導入により安全を確保し、通所介護での入浴支援および社会交流の機会を作りましょう。また、訪問看護により体調管理と生活状況の把握を行い、定期受診や家族との連携も含めて多面的な支援を行います。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
| 屋内外の移動に不安があり、転倒リスクが高い 安全な住環境で安心して生活を継続できる | 屋内外の移動で転倒なく生活できる | ・手すりの貸与 (廊下・玄関の安全な移動に必要) ・ 歩行器の貸与 (安全な屋外歩行用に必要) | 福祉用具 | |
| 寝室で安全に寝起きができる | ・特殊寝台及び付属品の貸与 (安全な寝起きのために必要) | 福祉用具 | ||
| 孤立感を感じており、社会的な交流が不足している | 身体的な健康を保ちながら、気兼ねなく他者交流ができる | 定期的に入浴を行い、清潔保持を維持する | ・入浴の一部介助及び見守り | 通所介護 |
| 社会的なつながりを増やし、精神的安定を図る | 他の利用者との交流を促進し、楽しみを見つける | ・他者交流 ・イベントの参加 | 通所介護 | |
| 健康管理や服薬確認が独居では難しい | 緊急時でも頼ることができ安心して在宅生活が続けられる | 体に異変があれば連絡・相談ができる | ・緊急時の電話対応 ・必要があれば訪問 | 訪問看護 |
| 定期的な健康管理で体調を安定させる | 健康状態を把握し、体調の悪化を未然に防ぐ | ・健康管理及び相談 ・服薬確認 | 訪問看護 | |
| 家族との関係性を維持し精神的安定を図る必要がある | 家族とのつながりを維持し、安心感を持つ | 定期的に家族とのコミュニケーションを取る | ・家族による通院同行 | 家族・セルフケア |
支援経過・解説
訪問時、屋内では手すりを活用し安全に歩行しており、屋外では歩行器の使用によって転倒の不安が軽減されている。
デイサービス利用時は、入浴支援を受けており、表情も穏やかで、「通うのが楽しみ」との言葉も聞かれた。
訪問看護では、バイタル確認や服薬状況のチェックを実施。体調は概ね安定しており、必要時には主治医との連携も図っている。
娘は月1回の通院に同行しており、本人の安心感に寄与している様子。サービス全体の効果も高く、現行支援の継続が望まれる。

このケースでは、認知症による不安定な生活状況に対し「住環境整備・健康管理・社会的交流・家族支援」をバランスよく組み合わせることで、安全性と精神的安定を両立できている事例です。
とくに、歩行器の導入とデイサービスの定期利用が、利用者の安心感と生活の質の向上に大きく貢献しており、今後もこの状態を維持することを目指していきたいと考えています。
認知症・独居(福祉用具・通所介護・訪問介護・訪問看護)
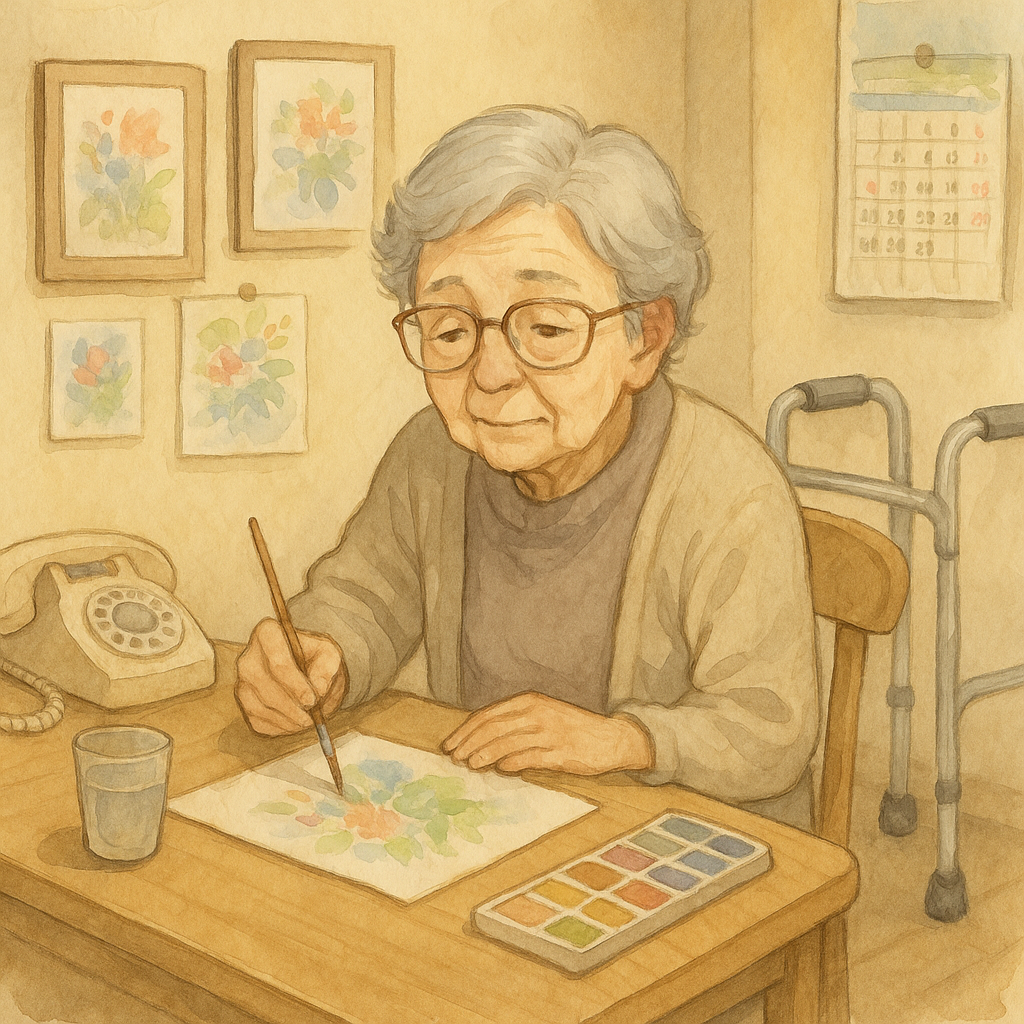
| 年齢 | 79歳 |
| 性別 | 女性 |
| 要介護度 | 要介護2 |
| 介護者 | 独居(身寄りなし) |
| 既往歴 | 認知症・慢性腰痛 |
| 状況 | 食事の準備ができず、買い物に不安あり。閉じこもりがちで社会的交流が乏しい。 |
| 本人の意向 | 家で暮らしたい。痛いのは嫌だ。なるべく人の手を借りずに生活したい。 |
| 家族の意向 | 身寄りがないため、意向の聞き取りはできず。 |
| 課題分析の結果 | ・認知症により段取りを組んで調理ができず、栄養状態の悪化が懸念される。 ・腰痛によって買い物や移動に支障がある。 ・社会的孤立や閉じこもりが見られ、うつ的傾向も一部確認される。 |
| 総合的な援助の方針 | 食事支援と買い物支援を組み合わせ、生活リズムの安定と安全を図る。 福祉用具により移動を補助し、転倒予防に努めるとともに、通所介護による入浴・交流支援を通じて生活の活力を引き出す。 訪問介護では日常生活の支援を行い、訪問看護で健康管理・服薬支援を実施する。身寄りがないため、多職種での連携により孤立を防ぎ、安心して暮らせる体制を整える。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
| 安全に屋内を移動したい | 転倒なく自宅で安心して過ごせる | 手すりや杖の使用で歩行が安定する | ・手すりの貸与 ・杖の貸与 | 福祉用具 |
| 栄養バランスの取れた食事を摂りたい。 | 健康を維持しながら自宅で生活する | 支援を受けて毎日食事がとれる | ・食事の準備 ・調理支援 | 訪問介護 |
| ・配食サービスの利用 | 配食サービス | |||
| 足が悪く買い物に行くのが不安。 | 自力または支援を受けて必要な物を購入できる | 買い物の回数や方法が安定する | ・買い物代行 ・買い物同行 | 訪問介護 |
| 入浴ができておらず清潔が保てていない。 | 定期的に入浴し清潔を保てる | 週2回以上の入浴が可能になる | ・入浴介助及び見守り | 通所介護 |
| 人と話す機会がなくなってきて寂しさを感じる | 気兼ねなく人と話し、精神的に安定する | 通所介護などでの交流を楽しみにできる | ・会話 ・交流機会の提供 ・レクリエーション | 通所介護 |
| 身だしなみが整い、デイサービスに行くことができる | ・外出の準備 ・整容の声かけ | 訪問介護 | ||
| 健康状態や服薬の管理ができない。 | 健康管理を行い、安心して在宅生活を送る | バイタル確認と服薬支援が習慣化する | ・バイタル測定 ・服薬支援 | 訪問看護 |
| 必要なときに相談できる体制を確保する | 訪問看護と連携し安心できる | ・緊急時対応 ・必要時の訪問 | 訪問看護 |
支援経過・解説
訪問介護と配食サービスで、週に数回の食事支援が行われており、栄養バランスが改善傾向。本人からは「温かいご飯が食べられてうれしい」との声あり。買い物も同行により必要物品の確保が可能となっている。
通所介護の利用により入浴支援が安定し、清潔保持が図れている。交流の中で笑顔が見られる場面も増加。レクリエーションへの参加も積極的になり、閉じこもり傾向の改善がみられる。
訪問看護ではバイタルチェックと服薬支援が継続されており、体調は概ね安定。緊急時にも対応可能な体制が整っており、安心感につながっている。

このケースでは、認知症による生活機能の低下や社会的孤立に対し、「生活支援・福祉用具・交流の機会・健康管理」を組み合わせることで、在宅生活の継続と安心感の確保を図っています。
特に、食事支援と通所介護での交流が、生活のリズムと精神面の安定に大きく寄与しており、今後も支援体制の継続と見直しを行いながら、孤立を防ぐ支援が求められます。
認知症・高齢夫婦世帯(福祉用具・通所介護・短期入所生活介護)

| 年齢 | 88歳 |
| 性別 | 女性 |
| 要介護度 | 要介護2 |
| 介護者 | 夫(同居・高齢) |
| 既往歴 | 認知症 |
| 状況 | 家の中での転倒や事故が複数回発生。 閉じこもりがちで活動性が低下。 夫の介護負担が増大し疲弊気味 |
| 本人の意向 | 家で暮らしたい。良いようにしてください。 ※認知症の進行により状況を十分に把握できていない。 |
| 家族の意向 | 一人で介護することに限界を感じており、介護サービスを積極的に活用してほしい。 |
| 課題分析の結果 | ・認知症による判断力の低下から、室内でも転倒や事故を繰り返している。 ・閉じこもりがちで認知機能の更なる低下が懸念される。 ・夫も高齢であり、心身ともに介護負担が増している。 ・本人の意向と安全確保のバランスが課題。 |
| 総合的な援助の方針 | 自宅内の転倒リスクを軽減するために福祉用具を導入し、安全な住環境を整える。 閉じこもりの改善と入浴支援のために通所介護を活用し、交流や刺激の機会を確保する。 短期入所生活介護を適宜利用し、夫の介護負担軽減と本人の生活リズムの安定を図る。 全体としては「在宅生活の継続」と「家族の介護負担軽減」の両立を目指す |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
| 自宅内外で安全に過ごしたい。転倒はしたくない。 | 転倒や事故なく日常生活を送る | 福祉用具を使用して安全に移動できるようになる | ・手すり設置 (廊下を安全に歩くために必要) | 福祉用具 |
| ・歩行器の貸与 (屋外の歩行の転倒防止に必要) | 福祉用具 | |||
| 家のお風呂場を使用すると目を離した隙に掃除をしたりして事故をしてしまうので助けてほしい。 | 清潔を保ちながら快適に暮らす | 週に数回の入浴が安定して行える | ・入浴一部介助及び見守り | 通所介護 |
| 短期入所生活介護 | ||||
| 人と話す機会が減ってしまったが本当は社交的なので人との交流を楽しみたい。 | 心の安定と活動意欲を維持する | 通所介護での交流を習慣化する | ・レクリエーション参加 ・職員が間に入り利用者とコミュニケーションを促進する | 通所介護 |
| 家族の介護負担を減らしたい | 夫が無理なく介護できる環境を整える | 定期的な休憩日が確保される | ・ショートステイの利用 ・身の回りの介護全般 | 短期入所生活介護 |
| これからも夫婦で少しでも長く家で暮らしたい | 住み慣れた家での生活を継続する | 安全性を確保しつつ在宅生活を維持する | ・全体的な支援体制の調整 | ケアマネージャー |
支援経過・解説
福祉用具の導入により、室内での転倒リスクがやや軽減。特にトイレ・廊下での移動が安定してきている。夫からも「安心して見ていられる」との声がある。
通所介護の利用が始まり、週2回の入浴支援とレクリエーション参加を継続。少しずつ笑顔が見られ、職員との会話にも反応が出てきている。
短期入所生活介護を月1回利用しており、夫の心身のリフレッシュにつながっている。今後は利用頻度の見直しも視野に入れて、家族の負担軽減をさらに進める予定。

このケースでは、「本人の安全な在宅生活」と「高齢の夫の介護負担軽減」の両立が大きなテーマです。福祉用具の導入による安全確保、通所介護での入浴・交流支援、ショートステイによるレスパイトといった複数の手段を組み合わせることで、安定した在宅生活の継続を図っています。
今後も夫の体調や介護力を注視しながら、必要に応じてサービス内容の調整を行い、無理のない支援体制を整えていくことが重要です。
軽度認知症・独居(福祉用具・訪問看護・訪問介護・夜間対応型訪問介護)
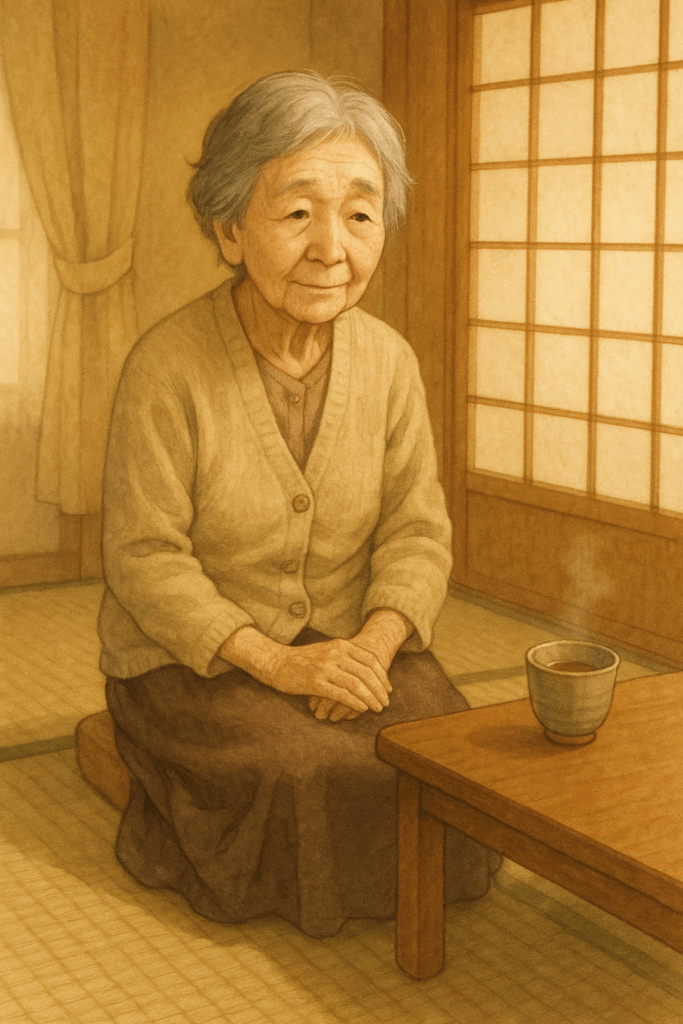
| 年齢 | 93歳 |
| 性別 | 女性 |
| 要介護度 | 要介護2 |
| 介護者 | なし(独居)※週数回、長男・長女が交代で訪問し食事や掃除は行なってくれている |
| 既往歴 | 心疾患 |
| 状況 | 食欲不振・歩行不安・閉じこもりがち |
| 本人の意向 | 家で静かに過ごしたい。デイサービスは嫌だし本当は他人に来てほしくない。 |
| 家族の意向 | 本人の希望を尊重したいが転倒が心配。できるだけ安全に過ごしてほしい。 |
| 課題分析の結果 | ・歩行不安と閉じこもり傾向が強く、転倒リスクが高い。 ・食欲も低下しており、体力低下の恐れがある。 ・本人はサービス利用に抵抗があるため、強い介入は逆効果になりやすい。 ・見守りと安心感を得られる環境づくりが急務。 |
| 総合的な援助の方針 | 本人の意向を最大限尊重しながら、最小限のサービスで安心・安全な生活を支える。福祉用具を活用した転倒予防と、夜間を含む見守り体制を整備し、在宅生活の継続を支援します。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
| 足腰が弱くなってきている。転倒するのは嫌だ。 | 転倒なく日常生活を送る | 福祉用具を使って家の中を安全に移動できる | ・手すりの貸与 (安全に廊下を移動するために必要) | 福祉用具貸与 |
| 安全に寝起きができる | ・特殊寝台及び付属品の貸与 (安全に寝起きするために必要) | 福祉用具貸与 | ||
| 家族の対応で安全に病院へ通院ができる | ・車いすの貸与 (安全に屋外を移動するために必要) | 福祉用具貸与 | ||
| 特に夜は家族に迷惑をかけたくない。何かあったときに助けを呼べるようにしたい。 | 夜間も安心して生活できる | 夜間対応の体制が整い安心感が得られる | ・転倒、排泄介助など困ったときの身体介護 ・緊急時の連絡体制の確保 | 夜間対応型訪問介護 |
| 家族が仕事の時も困った時に助けを求められる | 家族が安心して仕事ができる | ・24時間の訪問介護(身体介護) ・転倒、排泄介助等の対応 | 訪問介護 | |
| 体調の変化を早期に把握したい | 病状が安定し悪化時の早期発見が行えて安心して在宅生活が継続できる。 | 定期受診で病状が確認できる | ・定期受診 | 家族 |
| 定期的に健康チェックを受ける | ・バイタチェックと状態観察 ・予後予測 ・傾聴 | 訪問看護 | ||
| 体調の不安が相談できる | ・体調異変時の電話対応 ・必要時の訪問 | 訪問看護 |
支援経過・解説
・福祉用具導入(4月初旬)
手すりと特殊寝台の導入により、ベッド周囲やトイレ移動時の安定感が向上。本人も「これがあれば起きるのが楽」と話す。
・訪問介護(4月5日~)
初回は緊張した様子だったが、同じスタッフが丁寧に声かけしながら対応したことで、2回目以降は少しずつ受け入れが進む。
・訪問看護(4月7日~)
毎週バイタルチェックを実施し、食欲や排泄の様子も確認。異常はなく、家族にも報告を行って安心感を共有。
・夜間対応型訪問介護(4月10日~)
実際のコール利用はないが、「何かあっても頼れる先がある」ということで夜間の不安が軽減され、睡眠状況も安定。

このケースでは、本人の強い在宅希望と他人との関わりを避けたいという意向に配慮しながらも、安全と健康管理を最小限のサービスで実現する支援が求められました。
福祉用具を活用した転倒予防、訪問介護や看護による最低限のケア、夜間の不安を軽減する体制づくりにより、本人のリズムを守りながら安心できる環境を整えています。「無理にサービスを押し付けない」「顔ぶれを固定する」といった小さな配慮が、本人の受け入れやすさに繋がるのではないでしょうか。
今後もサービスの量や頻度は本人の変化に合わせて柔軟に調整し、穏やかな在宅生活の継続を支援していきます。
パーキンソン病
80歳・パーキンソン病・下肢筋力低下
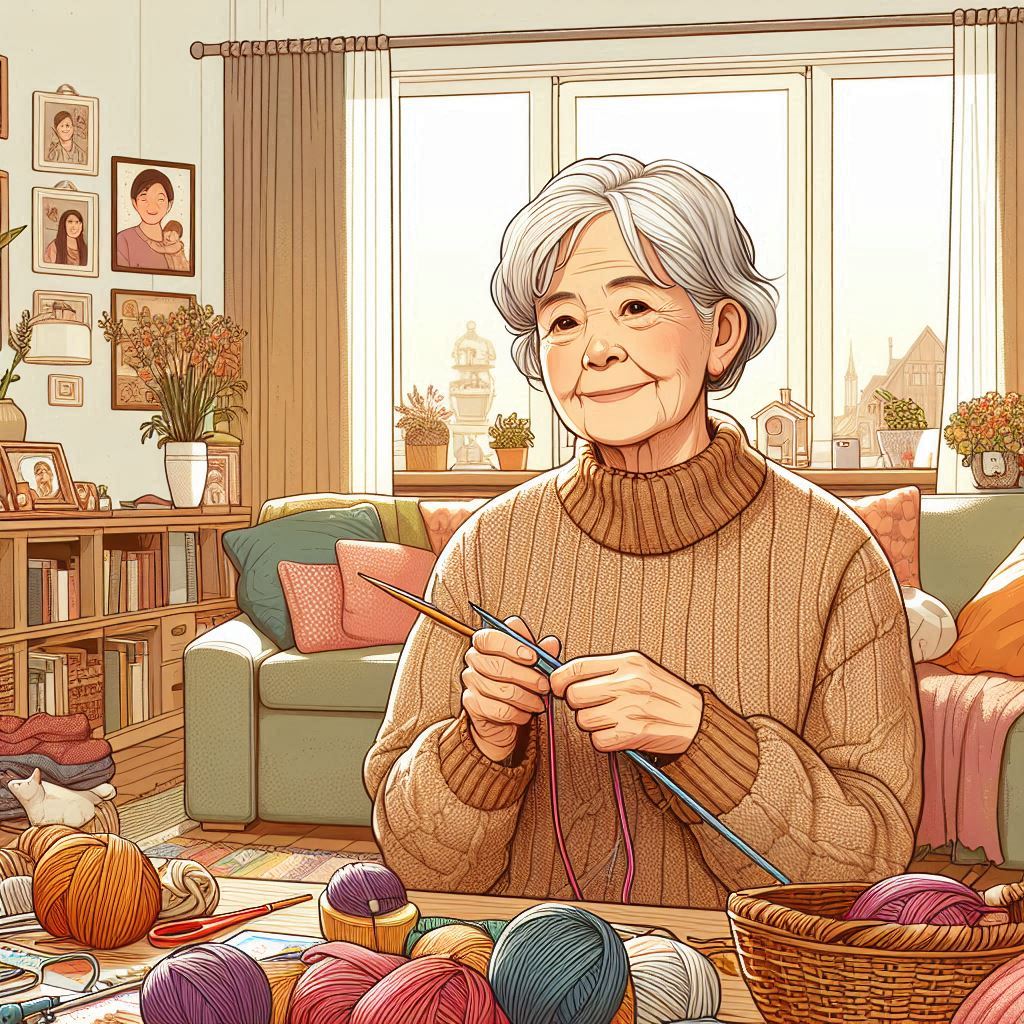
| 氏名 | D子さん |
| 年齢 | 80歳 |
| 病歴 | パーキンソン病・廃用性症候群診断 |
| 生活歴 | 70歳の頃に夫を亡くし、78歳の時にパーキンソン病の診断。現在、定期的に病院で経過観察を行い、薬物療法を受けている。大きな症状は出ておらず安定してるが、徐々に下肢筋力が低下しており、自力での歩行が困難になってきている。2人の子とは別居しているが、現在1人の孫(29歳)と同居している。日中は独居。買い物は近くに住む妹が時折手伝ってくれるが、妹も心臓に病気を持っている。喋るのが好きで、近所にも友人は多い。 |
| 本人の意向 | できる限り自立した生活を送りたいと希望しています。特に、家族との交流や近隣とのコミュニケーションを楽しみながら、社会的なつながりを保ちたいと考えています。また、趣味の手芸や編み物を続けたいという強い意志があります。 |
| 家族の意向 | 母が自分の家で快適に暮らせるように支援したいと考えています。父を亡くしてからも大変な日が続いていたので、楽しい思い出を作り続けてほしいです。買い物や日常のサポートを続けたいが長く続けられるかが心配。 |
| 課題分析の結果 | パーキンソン病に伴う運動機能の低下と下肢筋力の低下により、転倒リスクが高い。 独歩が困難なため、日常生活動作に支援が必要。 コミュニケーションを楽しむ一方で、孤立感を防ぐための社会的なつながりが重要。 趣味の手芸や編み物を続けるための環境整備が必要。 |
| 総合的な援助の方針 | 自宅での安全な生活環境の確保:住環境を見直し、安全に在宅生活が継続できるよう支援します。 身体機能の維持と転倒予防:定期的なリハビリと運動計画を導入し、筋力の維持と転倒予防に努めましょう。 社会的なつながりの維持:介護保険サービスを利用し、D子さんが社会的な交流を続けられるよう支援します。 趣味活動の支援:手芸や編み物を続けるための環境を整え、充実した生活を送りましょう。 家族との協力体制の強化:家族と連携し、D子さんの生活を支えるためのサポート体制を強化します。 |
| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | サービス種別 |
| 定期的に受診を続けて、パーキンソン病の症状の悪化を緩やかにしたい。 | 病状の管理ができて、安心して在宅生活が継続できる。 | パーキンソン病の症状をコントロールできる。 | ・定期受診 ・服薬管理 | 家族 医療機関 |
| 動き出しや立ち止まる時に思うように動くことができず転倒してしまうことがある。 | 転倒することなく、自宅で安心して生活を続ける | 家の危険箇所が減り、転倒することがなくなる。 | ・特殊寝台及び付属品(起き上がり時に必要) ・手すり設置(必要に応じ住宅改修) | 福祉用具貸与 |
| 今の動ける体を維持したい。できればもっと動けるようになりたい。 | 現在の身体機能が維持向上し、転倒が予防できる。 | 定期的な運動で、身体の柔軟性を維持し筋力の向上が目指せる。 | ・個別機能訓練 ・マシントレーニング ・口腔機能向上訓練 ・入浴 | 通所介護 |
| 人とのコミュニケーションは好き。1人でいるのは寂しい。 | 積極的にコミュニケーションを取り、寂しさが解消される。 | 定期的に外出し、社会的な交流を続けられる。 | ・他者との交流 ・レクリエーション | 通所介護 |
| 自分でできないことが多いが、自分のことは自分でしたい。 | 身の回りのことが行えて、自信を持って自宅で過ごすことができる。 | できるだけ身の回りのことが行える。 | ・家事全般の自立支援(洗濯・掃除) ・買い物代行(希望時は同行も可能) ・デイサービスの準備 | 訪問介護 |
| これからも趣味である手芸は続けたい。 | 手芸や編み物を続けられ、楽しみが増える。 | 必要な道具や材料を揃えられる。 | ・手芸用品の購入 ・手芸活動のサポート | 家族 |
| (家族より)これからも母が自宅で過ごせるよう家族でも話し合いたい。 | 家族と連携し、安心して生活を支えることができる | 家族と定期的にコミュニケーションを取り、サポートを調整する | ・定期的な家族会議の開催 ・連絡手段の確保 | 家族 ケアマネ |